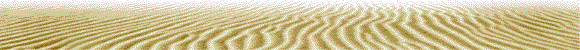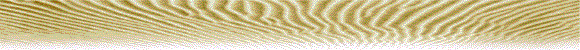
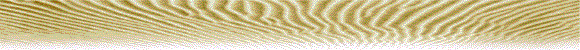
| 70 | 60 | 智慧と慈悲 | |
| 69 | 59 | ||
| 68 | 58 | 愚痴の病 | |
| 67 | 57 | 「いのちに合掌」 | |
| 66 | 56 | 「やおよろず」という見方 | |
| 65 | 55 | 善いことをする | |
| 64 | 54 | 自然の治癒力 | |
| 63 | 53 | 共生の社会を | |
| 62 | 52 | 「幸せ」について | |
| 61 | 唱題のこころ | 51 | 自己を知る |
| 50 | 災害列島に生きる | 25 | 仏性を育てる |
| 49 | 「非暴力」のちから | 24 | 不殺生戒について |
| 48 | 「冥福を祈る」とは | 23 | 貧富の二極化現象に想う |
| 47 | 物から心へ | 22 | 「盲亀浮木」の譬え |
| 46 | 日本のよさを見直す | 21 | 「仏涅槃図」に想う |
| 45 | 他者のために | 20 | 望ましい生き方 |
| 44 | 心の安らぎを求めて | 19 | 柔軟心ということ |
| 43 | 「悟り」ということ | 18 | 命を賭して信を貫く |
| 42 | 懺悔とは? | 17 | 怨みの連鎖を断つ |
| 41 | すべての衆生を救わん | 16 | 社会のために |
| 40 | 執われの心 | 15 | 智慧をまなぶ |
| 39 | すべてに価値あり | 14 | 悲しみに打ち克って |
| 38 | 「無限」の可能性 | 13 | ことばは心を映す鏡 |
| 37 | 暗闇の復権 | 12 | 心の財(たから)第一なり |
| 36 | 花祭に因んで | 11 | 適応力を取り戻す |
| 35 | 合掌のこころ | 10 | 生かされて生きる |
| 34 | 「人生は苦」か? | 9 | 精進するということ |
| 33 | 彼岸の修行 | 8 | お祖師様へのご報恩 |
| 32 | いじめを考える | 7 | いのちを伝える |
| 31 | 江戸の商法を見直す | 6 | 仏種を開花させる |
| 30 | 企業人の志 | 5 | 地上に人が住めなくなる! |
| 29 | 祈りの力 | 4 | 万物と共に生きる |
| 28 | 慈悲の心で | 3 | お盆のいわれ |
| 27 | 臨終の事を習ふ | 2 | 「させていただく」という心 |
| 26 | 「立正安国」の教え | 1 | 立教開宗とご法難 |
「南無妙法蓮華経」をお題目といい、日蓮宗では、お題目を唱えることが「正行」と言って最も大切な行とされます。
それでは、お題目はどのような心で唱えればいいのでしょうか。単に呪文のように唱えるだけでいいという考え方もありますが、ここではその意味について考えたいと思います。 ◇ まず、「南無」とは、梵語「ナーモ」の音訳で「帰命」と訳し「命をかけて帰依します」という意味です。従って、「南無妙法蓮華経」とは、お釈迦様の真実の教えである「妙法蓮華経」(略して法華経)の教えに、心から従い実践します、という意味になります。 ◇ それでは、「妙法蓮華経」とは、どのような教えなのでしょうか。「妙法蓮華経」の原語は、梵語で「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」といい、サット=正しい、ダルマ=法、プンダリーカ=白蓮華、スートラ=経で、「白蓮華のような正しい教えの経典」となります。 訳者・鳩摩羅什は、正しい教えを「妙法」と訳します。妙とは、不可思議の意で、人間の智慧では計り知れない奥深いという意味です。 次に、白蓮華ですが、「この泥があればこそ咲け蓮の花」(蕪村)とあるように、白蓮華は高原の清らかな水では成育しません。低地の泥水の中で、泥を栄養として育ちますが泥にまみれない清らかな花を咲かせます。 悪もはびこる俗世(泥)の中に暮らしながら、それに染まることなく清らかに自由に生きるという人の理想的生き方を示します。これは菩薩様の生き方でもあります。 「蓮華は水に生ずるも、還って水に著せず。菩薩は俗に在るも俗に拘へられず」 (天台大師・智顗『澄心論』) とあるのがそれです。 つまり、「白蓮華のような正しい教え」とは、菩薩様の生き方をお手本としなさいということです。 それでは、菩薩様の生き方(菩薩行)とはどのようなものかというと、 「上求菩提・下化衆生」という言葉で表されます。 目指すところはは菩提(悟り)を求め(=自利)、下に向かっては衆生(生きとし生けるもの)を教化する(=利他)ということです。 ◇ 従って、「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えるということは、 「どうか私に仏様の智慧をお授けください。私はそれを悩む人に分け与え社会に役立ててまいります。」、 と誓願することだと考えるのが良いと思います。 ◇ 日蓮聖人は「一生成仏抄」に、「錆びた鏡も磨けば、清らかな鏡になるように、私たちの迷う心も日夜朝暮に磨けば悟りの明鏡になる。磨くとは何か。南無妙法蓮華経と唱えることが磨くということなのだ。」(枠中のことば)と示しています。 ◇ 法華経を始めとして、お経とはその教えが尊いのだと思います。その教えを理解し実行する、つまり人の役に立つような生き方をする中で、その人の心も健康も整ってくる、これが宗教の救いということだと思います。 ただやみくもにお題目を唱えればいいという次元から、少しでも法華経の精神を理解し、誰もが、その心構えを込めてお題目を唱え、その実践に努めるならば、立正安国の願いが達せられるのも夢ではないといえましょう。 |
「老齢は智慧の塊」と言います。
しかし、それとは逆に徐々に蓄えら れるものがあります。それが「智慧」 です。私たちは、生まれて物心がつい てから、誰もが少しでも自分を向上さ せたいという思いで一所懸命に生きま す。一日一日が新しい体験であり、学 びとなり、それらがすべて智慧として 蓄積されて行くのです。 ◇ 人は人生を生きる中で、喜びや悲し み・苦しみ・怒り…と様々な体験をし ます。人生は苦、と言われる以上、暮 らしの中で次から次へと難題が湧いて くるのが当たり前。そして、それら一 つ一つに真剣に向き合い、解決してい く中で、人間性が育まれ、智慧が蓄え られるのです。 いじめなどの問題も、相手側の立場 になって考えれば、その人の人生ばか りでなく、その家族の生活まで破壊し てしまうことにも思いが巡るはずであ り、また、災害などで肉親を亡くした 悲しみなども、同様な自分の体験に照 らせば、悲しみの深さも理解でき、ふ さわしい対処の仕方もおのずと出てく るものだと思います。 ◇ 中国の思想家・孔子は、「先生、たっ た一語で、一生それを守っておれば間 違いのない人生が送れる、そういう言 葉がありますか。」という弟子の問い に対して、「それは『 確かに、常に相手の立場に立って考 える生き方ができれば、人からの信頼 も得られるし、その人の幸せ感となっ て戻ってくると言えましょう。 孔子と言う生き方の達人のことばだ けに、重みがある一言です。 ◇ 仏教のことばに、「慈悲」があります。 慈は、衆生に楽を与える、悲は、苦 しみを抜く意で、「 「仏・菩薩が衆生をあわれみ、いつく しむ心。」(広辞苑)で、特に仏・菩薩 の大事な役割となっています。 特に、仏・菩薩の広大無辺な慈悲を 「大慈大悲」と言い、観世音菩薩の徳 を表すのに多く用います。 「大慈は、一切衆生に楽を与え、大悲 は、一切衆生の苦を抜く。」(枠中の語) とあるのがそれです。 ◇ 人の理想の生き方は、菩薩様のよう に生きること(菩薩行)と言われます。 菩薩様は、自分の修行に励んで仏の境 地に達することを目指し、同時に悩み 苦しむ衆生があれば、慈悲の心を以っ てそれを救うことを役割としていま す。 私たちも、誰もが自己の向上を図る と共に、お互いの苦境には、それぞれ の智慧を以って手を差し伸べあいたい ものです。 「慈悲あるものは怨みを得ず」(釈尊) とありますが、そのように実践するこ とは、人から恨まれることもなく、そ の人自身にも福をもたらすことになる のです。 ◇ 「智慧と慈悲」とは、仏教の修行で獲 得すべき二大徳目といわれ、また、一 体のものとも思われます。 私たちは、智慧を蓄え、それを以っ て慈悲に繋げたい。特に高齢者として は、体力では若い人たちに及ばないな がら、子育てや貧困に苦しむ人々が増 えている現代社会で、智慧 と慈悲で貢献していきたい ものです。 |
9月の鬼怒川決壊による茨城県常総市の洪水災害、昨年の広島・安佐地区、一昨年の伊豆大島の土石流災害などがそれです。いずれもかつて無かったと言われる豪雨による大規模な災害で、地球温暖化に起因すると思われます。 そして、これからもこのような異常気象が当たり前のようになってくると、たくさんの被災者が出て、私たち人類の文明の存立が危うくなってくるとさえ言えましょう。 ◇ 地球の温暖化は、ある地域には、寒冷化をもたらすと言われます。つまり、温暖化すると、南極や北極の氷が大量に融けて海水の濃度が薄まり、海水の熱を蓄える働きが弱まる。すると、暖流の流れる地域の気象に影響するというわけです。 中米のメキシコ湾からイギリス・北欧の方に流れる通称・メキシコ湾流と呼ばれる世界最大級の暖流がありますが、この暖流は、イギリスなどヨーロッパの高緯度地域を温暖な気候に保つのに重要な役割を果たしています。この暖流の温度が下がると、北欧・ヨーロッパ・イギリスなどは、大体日本の札幌より高緯度ですから、寒冷化・凍土化して人の住めないような土地になってしまうということです。〔ペンタゴン(米国防総省)レポート〕 ◇ また、温暖化は、海面上昇によって、土地を水没させたり、乾燥により砂漠化させたりして、人の住める範囲は限定されてしまいます。 このように見ると、現在世界では戦争や民族紛争による難民が増えて混乱状態を招いていますが、これからはそれに加えて環境難民が急増し、世界はさらなる混乱状態に陥ることが予想されます。 ◇ もしかすると、文明の崩壊は、既に始まっているのかもしれません。 「茹でガエル」という比喩をご存知でしょうか。 カエルを熱湯に近付けると熱さを感じて逃げてしまいます。しかし、鍋の水の中にカエルを入れてガスをつけて沸かしていくと、カエルは温度の変化に気づかず、やがて気がついた時にはそのお湯から抜け出せなくなっていて、やがては茹であがって死んでしまう、という話です。 近年、世界では、異常気象によると思われる災害が多発しています。 今年に限っても、8月の台風13号では気圧が900ヘクトパスカルにまで下がり、風速58㍍の猛威で、台湾・中国では大暴風・大洪水による被害の他、巨大な竜巻が発生して、多くの物的・人的被害を出しています。5月には、インドに猛烈な熱波が襲い、死者数千人、ニューデリーでは道路が溶けたと言われます。その他、オーストラリアの大干ばつ、アメリカ・カリフォルニアの山火事の多発、大洪水・土石流・熱波・寒波など、記録的に猛烈なものが増えています。 ◇ それにもかかわらず、私たちは更なる快適さを求めて、物を大量に消費し続けています。 先日の新聞に、宅配便の不在者への再配達についての記事がありました。 それによると、「再配達には、延べ年間約1億8千万時間かかり、労働力に換算すると約9万人分になる。トラックの排ガスでは年42万トンの二酸化炭素が発生。これは、山手線の内側面積の2・5倍と同じ広さのスギ林が吸収する量に匹敵する。」とのことです。(朝日・H27・10・3) もう私たちは、鍋の中のカエルの様にかなり茹であがった状態にあるのかもしれません。 ◇ 釈尊のことばに 「知足の人は地上に臥すと雖ども、なお安楽なりとす。」(『仏遺教経』) 足ることを知っている者は地べたに寝るような生活であっても幸せを感じている。とあります。豊かな物量に囲まれなくても、幸せに暮らせるということです。 文明の崩壊とは、多くの災害が起き、世界は無政府状態となり、多くの人が苦しむ状況になることです。子や孫たちの時代がそうならないように私たちも意識を転換し、また、政治にもしっかりとした政策を採って欲しいものです。 |
このように書くと、日本は水資源が有り余っているように思われますが、現実はまったく違っています。 ◇ そもそも地球は水の惑星といわれますが、実はその98%が海水で、淡水は2%に過ぎず、しかもその大部分は南極や北極の氷山などで、私たち陸上生物が利用できる水は全体の0.01%にも満たないのです。地球上の水すべてが風呂桶1杯の水だったとすると、私たちが使える水はわずかに1滴で、この1滴の水をすべての陸上生物が分かち合って生きているのです。 ◇ 日本の水事情は、一見恵まれているように見えます。確かに、世界平均の年間降水量が973㎜に対し、日本のそれは1、800㎜で約2倍です。しかし、国土が狭いので、1人あたりの年間降水量に換算すると、格段に少なくなり、世界平均の4分の1にも満たず、世界で82位となってしまいます。 それにもかかわらず、清潔志向の私たち日本人は、髪を良く洗い、真っ白なシャツを着て、水の消費では世界で第4位の位置を占めているのです。なぜそれが可能かと言えば、それは、私たちが《仮想水》という形で水を大量に輸入しているからです。 1㎏のトウモロコシを生産するには、1、800ℓの水が必要です。また、牛はこうした穀物を大量に食べて育つため、牛肉1㎏を生産するには、その約2万倍もの水が必要となります。ということは、日本は海外から大量に食料を輸入していますが、それは、形を変えて水を輸入していることと考えることができます。それが仮想水で、その量は、約800億㎥であり、日本国内で使用される年間の水の使用量とほゞ同量になります。 日本人は海外の水に依存して生きているといえるのです。 ◇ 話は変わって、日本の医療を見ると、すべての国民が公的医療保険制度でカバーされており、保険証があれば、どの医療機関にもかかれ、たいていの医療が保険によって賄われます。人工透析にしても、患者は30万人と言われますが、患者にとって保険はまさに命綱であり、なくてはならないものとなっています。 他国を見ると、フランスでは、かかった医療機関の区分によっては医療費が一定額を超えると自己負担する必要があったり、またドイツでは、大学病院での受療には紹介が必要で、患者が必ずしも自由に医療サービスを選べるわけではありません。スウェーデンでは、医療費は無料に近いが、1週間以内に医師に診てもらえるようにすることが、医療政策の目標になっているとのことです。アメリカでは、昨年まで医療保険制度が整備されておらず、数千万人が無保険者で経済的理由で、病気になっても医療に掛かれませんでした。 このように見ると、日本の国民皆保険制度がいかに優れた制度であるかが分かると思います。 私たちは、水の使用についても、医療にしても、空気のように当たり前で、その「ありがたみ」を自覚していないように思われます。 ◇ 「涅槃経」に、三毒の病の治療法として 「貪欲の病には骨相観を、瞋恚の病には慈悲観を、愚痴の病に縁起観を教える。」 (意訳)愛欲に溺れている者には、相手がどんなに魅力的に見えても、所詮、骨でしかないと気付かせる。怒る者には、慈悲の心の大切さを説く。無明により誤った見方しかできない者には、縁起に基づく考え方を教える。とあります。 仏教では、3つの根本的な煩悩(=毒)として、貪・瞋・痴(とん・じん・ち)を挙げ、三毒と言います。「貪」は貪欲で、欲深く物をほしがる、「瞋」は瞋恚で、怒ること、「痴」は愚痴で、因果の道理に暗く実体のないものを真実のように思いこむこと、です。 この三毒は、人間の諸悪・苦しみの根源とされ、これを克服することが仏道修行であるとされます。 ◇ 2025年には世界人口の2/3が水不足になると予測されており、その原因の大部分は、先進国の水の大量消費です。やがて、そのつけは私たちの身にも及ぶでしょう。 また、皆保険で医療は安くて当たり前と錯覚し、感謝の念も薄れてしまえば、この制度も崩壊します。 縁起の考え方を理解し、「愚痴の病」を克服したいものです。 |
| イースター島という島があります。モアイという巨石の像が並び立つことで有名です。 この島は、太平洋の、南米大陸から3千7百㎞も離れたところにある絶海の孤島で、4~5世紀の頃は、巨大椰子が沢山生い茂る緑豊かな島だったといわれます。
代を重ねる毎に有力者が分家して部族の数が増え、島の到る所に、それぞれの部族の祭壇が作られ、1千体を超すモアイ像が造られました。大きさは高さ3m、重量20トンもあり、最大級のものは高さ20m、重量は90トンにも達します。 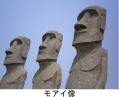 これらの巨石像を運ぶ資材にするため大量の木が切り倒され、森が失われ、森を失った島からは肥えた土が海に流れ出し、土地は痩せ衰えていきました。 海鳥以外の鳥類もとりすぎて絶滅し、人々は餓死するものが続出しましたが、木がないためカヌーをつくって島から逃げ出すこともできず、島内で争いあい自滅したと言われます。 これらの巨石像を運ぶ資材にするため大量の木が切り倒され、森が失われ、森を失った島からは肥えた土が海に流れ出し、土地は痩せ衰えていきました。 海鳥以外の鳥類もとりすぎて絶滅し、人々は餓死するものが続出しましたが、木がないためカヌーをつくって島から逃げ出すこともできず、島内で争いあい自滅したと言われます。1万人以上とも言われた人口も、西洋の船に発見されたのちに天然痘が猛威を振るったこともあり、19世紀後半には、わずかに100人余りに減ってしまい、原始人さながらの生活だったそうです。 ◇ 話は変わって、日蓮宗は平成33年に、「日蓮聖人ご降誕八百年」の記念の年を迎えます。そして、それに向けての活動として「いのちに合掌」というスローガンを掲げています。 言うまでもなく、私たちは自分一人では生きていくことはできません。人と人とが支え合い、動物・植物の命をいただき、その動植物もすべてお互いに恵みを施し合って共存しています。更には、生物のみならず、地球のあらゆる資源の恩恵を受けて、私たちの生活は成り立っているのです。 私たちは普段そのようなことは自覚することなく生活していますが、改めてそのことに思いを馳せて、あらゆる命・資源を尊び感謝しようというのが、このスローガンの意味するところです。 ◇ 現在、私たちの生活や、世界の現状を見ると、いかに資源を大量に浪費しているかが分かります。 石油については、前にも書きましたが、現在、世界全体では、只の一日で、ドラム缶(200㍑入り)で4千3百万本分の石油を消費しているとのことです。これは日本列島に(稚内から鹿児島まで)並べると11列にもなる膨大な量です。そして、その結果、年間60億トンもの二酸化炭素を大気中に放出しています。 森林の破壊も深刻です。毎年日本の国土面積の半分に当たる森林が消失し、その半分は草も生えない砂漠と化しています。世界最大の原生林アマゾンもあと50年で失われると言われ、フィリピン・インドネシアの熱帯林はほとんど伐採・焼却されて消失寸前の状態です。その主な原因は、私たち先進国による消費です。木材や新聞・書籍などの紙としての消費の他、森林を焼き払って農園とし、ヤシ油や果物を作って換金するのです。 そして、その焼却による二酸化炭素の排出量は、泥炭層の土地が引火により燻ぶり続けることもあって、世界中の車が排出する量に匹敵するとのことです。 ◇ こ のような人間の活動によって引き起される温暖化が、世界中で、 日蓮聖人は、『立正安国論』において、 近年より近日に至るまで、天変・地夭・飢饉・疫癘、遍く天下に満ち、広く地上に迸る。(枠中の語) と書かれ、民衆の苦しみに思いを馳せておられますが、世界の現状はこの鎌倉時代の状況をも ◇ これから、途上国の人々の生活水準が上がれば、問題はさらに悪化します。70億人もの人々が先進国並みになることに、地球の環境は耐えられません。 現代の私たちも、地球という孤立した島に住んでいます。地球環境を台無しにしてしまっても、イースター島の人々と同様に、別の星に移り住むことはできないのです。 この問題の解決法について、新聞に 「先進国の人々が資源やエネルギーの消費を落とす一方で、途上国の人々は消費水準を上げ、両方をバランスさせることだ。そうすれば、テロや難民の問題もおさまっていくだろう。」(朝日、H24・1・2「文明崩壊への警告」)確かにそれ以外の道はないように思われます |
「イスラム国」なる国家を自称する集団が、イラク・シリアなどで戦いを展開しています。
イスラム教スンニ派の集団で、武力を以ってイスラム世界のスンニ派への統一を図ろうということのようですが、目的のためには残虐な手段をも厭わない非人道的なやり方に、国際社会は世界の安全をも脅かすものとして苦慮しています。 ◇ 世界の各地で起きている争いごとを見ると、その大半は宗教が絡んでいるように思われます。そもそも自分の信じる教えを、他に強要しようという考え方はいかがなものでしょうか。 宗教においては、自分の所属する宗教・宗派を絶対的なものと考えがちです。特に、イスラム教やキリスト教など、「一神教」の教えでは、神は唯一・絶対のものとされます。それを個人的に信じることには、何の問題もありませんが、その教えで一国をあるいは他国をも統一しようと考える者が出てくると悲劇は起こります。かつて、キリスト教の十字軍が、何度にもわたってイスラム教圏に侵攻し、大量殺戮を繰り返したことなど、歴史的にも多数の例が見られます。 客観的に考えると、複数の宗教が自身を唯一・絶対とした場合、一つが正しければ他は必ず間違いとなるはずです。そう考えると、どの宗教も絶対と言えるものはなく、それぞれが長所も短所もあると考える方が自然ではないでしょうか。私たちは自分の信じる宗教を拠点として、他の宗教の長所も参考にしてゆくというあり方が良いのではないかと思います。 ◇ 釈尊の弟子・舎利弗の叔父に「長爪」と呼ばれる人がいました。彼は、根本経典をすべて読み尽くすまでは爪を切るまいと誓いを立てて長い爪をしていたそうです。 その彼が、多くの知識を身に着けて、手当たり次第に議論を仕掛けては、その相手を論破し、その勢いを以て釈尊に議論を持ち掛けます。そして、開口一番、「私はすべての教説を認めないと主張する」と嘯きました。 その時、釈尊は即座に「では『すべてを認めない』というその見解も認めないのですか」と切り返します。しどろもどろになる長爪を、釈尊は丁寧に諭してゆきます。すべてを認めないという主張もあり、すべてを認めるという主張もあり、部分的に認めるという主張もある。いずれにしても、世の中には様々な主張がある。そういうことを考えずに、自分の説だけに固執するなら、必ず対立して争論となり、余計な苦しみを増すだけでまったく無益である、と。 ◇ ところで、私たち日本人は宗教に関しては、無節操であると言われます。確かに、クリスマスにはケーキを食べ、七五三には神社にお参りし、葬式・法事は寺で、結婚式は神道、最近はキリスト教式が増えています。 しかし、これは見方を変えれば日本人の寛容性を表わすともいえるのではないでしょうか。 日本には昔から「八百万の神」といい、山には山の神、水には水の神と、山川草木・あらゆるものに神が宿っているという考え方があります。そこに、奈良時代に仏教が入って来たわけですが、これがとても日本的な考え方と折り合いが良く、仏教側からすれば、それを取り込んで日本的仏教を作り上げてきたと言えます。 仏教の言葉(枠中の語)に、「一切衆生 悉有仏性」があります。 「生きとし生けるものは、すべてが仏性を備え成仏する可能性を持つ尊い存在である。だから、すべての存在を尊重しよう。」ということで、八百万の神と同じく、人間も自然の一部で自然と共存しているという考えが根底にあります。 ◇ 日本の仏教は、釈尊を起源としますが、その後も釈尊の思想を広げ深めていろいろな経典が作られ、どれを重視するかで宗派が生まれました。しかし、「やおよろず」という基本的な見方が根底にあるため、前記の釈尊の言葉のような、一つの説に固執しない、様々な見方を認める寛容さを作り出しているものと思われます。 一神教的欧米の世界から見ると、「やおよろず」というようなものの見方は野蛮な原始宗教的なものに見えるでしょうが、実はこれこそが日本人の宗教に対する寛容さを形成する基になっており、宗教的な争いのない社会の維持に役立っているように思われます。 |
つひにゆく道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは思はざりしを
この歌は、平安時代の歌人・在原業平の辞世の歌です。 「(臨終というものは)誰もが最後には迎えねばならぬものとは、前々から聞いて知ってはいたけれども、(その臨終の時が)自分の身に、昨日今日というほどこんなに差し迫って訪れようとは思いもしなかったよ」 という意味で、人生八十年生きても、九十年生きても、誰もが最期の時にはこのような思いに囚われるのではないでしょうか。 ◇ 時間というものは止めどなく流れてゆくものだということを、最近しみじみと感じます。 朝、今日は楽しい旅行の日だなと思っていても、その日は瞬く間に過ぎて、夜を迎え翌日を迎えます。半年後に同窓会を計画し、まだ先のことと思っていても、時は確実に経過し、やがて過去の思い出となって行きます。 人の一生とは、学業を卒え、職に就き、結婚をして家庭を持ち、やがて、子の独立、親との別れ、…などと経過しますが、若い時は、遥か将来のことと思っていたこれらのことも、その時は確実に訪れ過ぎ去っていくのです。 私たちの臨終についてもまったく同じで、冒頭の歌のように間違いなくやってきます。 ◇ このように考えると、私たちは、人生の設計は別にしても、日々の暮らしにおいては、あまり先を見ずに目標は身近に立てて生きるのが良いのではないかと思います。 時間の流れの速さとは、主観によって左右されるのではないでしょうか。一年単位で物事を考えると、一年・二年は瞬く間に過ぎ去ってしまうように思えます。一日単位でなすべきことを定め、今日はそれが達成できた、次の日は、新たな一日として生きる、と考えた方が、一生が充実するような気がします。 ◇ 禅語に「日々是好日」という言葉があります。「にちにちこれこうにち」と読むのが本当だそうで、「にちにち」とは、一日一日が単独の日であることを意味します。 従って、雨降りにしても、「昨日は雨が降った」、「今日は雨が降っている」、という言い方となり、「昨日は雨、今日も雨」ではない、つまり、昨日と今日とは関係のない一日と考えます。そして、昨日は昨日で良い一日であり、今日は今日で、新しく出会った良い一日となります。昨日・今日・明日ということを関連付けることが、私たちの感情を複雑化する。こだわり、とらわれをさっぱり捨て切って、その日一日をただありのままに生き、清々しい境地に達する、これが「日々是好日」の心だそうです。 ◇ それでは、どのように生きたらよいかと言えば、仏教の答えは明快です。 「悪いことはしない。善いことをする。」ということです。 これは、「七仏通戒偈」に書かれていることで、全文(枠中の語訓読)は、 諸悪はです。 悪いことはせず、善いことをすると心はおのずと清らかになる。これが、どの仏様にも共通する教えということです。 何が善く何が悪いかの判断は難しいとしても、確かに、自分に悪いことはしていない、善いことをしているという自覚が持てれば心の平安に繋がります。 三歳の子供でも知っている簡単なことですが、なかなか守れないのが私たちです。しかし、あらゆる仏の勧める戒めですから、心して努めたいものです。 |
東日本大震災から丸三年が経ちました。
近親者が目の前で波にさらわれたり、配偶者や子供を一度に亡くしたり、などの過酷な体験が心の傷となり、強い不安や不眠の症状を訴える人が未だに多いといわれます。このような症状を「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」と言いますが、その心を癒すには、医師の適切な治療も必要なことながら、それにも増して「日にち薬」というように、時の経過が妙薬と言えましょう。 ◇ 私たち人間は、太古の昔から、自分の身体は自分の持つ自然治癒力で直してきました。「日にち薬」もその一種と考えられます。今はまだつらい状態にあっても、何年か後には必ず悲しみは和らぐことでしょう。 医療の発達により、病気の完治率は格段に高まりましたが、自分の身体を治すのは自分自身であるという原点は、いつになっても大切です。 ◇ ここで、私たち自身で出来るPTSDに対する対処法を考えてみたいと思います。 先ず、悲しみの癒し方としては、「涙を流す」ことです。 涙とは、眼を保護するための液体ですが、悲しみの涙には、通常の涙の三十倍ものマンガン(体調を維持するミネラルの一種)が含まれるとのことです。マンガンとは、体中でその血中濃度が高まると、うつ病になると言われます。つまり、私たちは悲しみの涙を流すことによって大量のマンガンを体外に排出し、うつ病になるのを防いでいると言えるのです。 また、涙を流すときは、脳からエンドルフィンというホルモンが分泌されます。エンドルフィンは「脳内モルヒネ」ともいわれ、薬品のモルヒネの六倍の鎮痛作用があり、多幸感をもたらします。 私たちは、涙を流すと不思議と心が落ち着くという経験があると思いますが、それはこのような作用によるのだそうです。 ◇ 次の対処法として、「十分間の唱題」をお勧めします。 唱題とは「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えることですが、これには「呼吸法」と「リズム運動」とが関係します。(読経でも同じです。) 「呼吸法」から説明すると、私たちは一分間に十五回くらい呼吸をしています。しかし、読経・唱題している時は、一分間に五呼吸くらいです。一秒で吸った息を十秒掛けて吐いている勘定です。これは、精神医学会も推奨している、吸った息を出来るだけ長い時間を掛けてゆっくりと吐くという健康法に合致します。 私たちは、吸った息を吐き切らないうちにまた吸ってしまっており、それが続くと、血管が収縮し、血流が悪くなります。ゆっくりした深い呼吸は、副交感神経の働きを高め、収縮していた血管が緩み、血液が体のすみずみまで流れ、心も体も甦ることになるのです。 次に、「リズム運動」についてですが、リズム運動は、セロトニンという心のバランスを整える物質を増やす働きがあることが分かっています。この物質が不足すると、疲れやすく、うつ病などの症状となり、満ち足りていれば、心の安らぎが生じます。 読経・唱題することは、自ずとこの呼吸法とリズム運動を同時に行うことになるわけです。私も、朝夕の読経・唱題のお蔭で健康が維持できているのかと思うとありがたい限りです。 ◇ 釈尊は、法句経に 「主とし頼りとするものは、おのれを置いて他にない。だから、おのれ自身を制御しなさい。」(枠中の語・意訳)と示しています。 最終的に頼れるのは、自分自身しかない。(しかし、その自分の判断は、法=真理に則って行なわなければならない。)だから、その判断ができるようにおのれを成長させなさい、ということです。 病についても、おのれが主役です。薬や医療に頼る前に、生まれながらに備わっている自然治癒力(免疫力)を働かせる生き方を心がけましょう。 |
紀元前五世紀頃のエジプトとバビロニアの医療の話です。
エジプトでは医術が多くの専門別に分化していて、それぞれの医者は一種類の病気のみを扱い、いくつもの病気を扱うことはなかった。従って、眼の医者、歯の医者、頭の医者、腹の医者、等々、多くの医者がいたが、全体を診断する医者はいない。 対して、バビロニアには、医者というものがいなかった。だから、病人がでると、家人は病人を広場へ連れて行く。すると、そこを通行する人が、病人を見て、自分が同じ病気を患ったことがあったり、少しでもその病気について知っている場合は、その病気についての知識や自分が治した時の療法を伝える。 そして、病人の傍を通行する人は、どんな症状かを尋ねずに、知らぬ顔をして通り過ぎてはならぬことになっていた。 (ひろさちや「闘病の思想と共生の思想」) これを読むと、今の日本の医療は、エジプト型かと思われます。ガン・心臓病とか、個々の臓器とかごとに専門化され、人の病を治すという原点が忘れられているように思われます。 ◇ これを裏付けるような話を、檀家のTさんから聞きました。 Tさんは、しばらく前に、足が痛くなり靴を履くのも不自由になりました。整形外科を二箇所回って、レントゲン検査などもして診てもらったが何が原因か分からない。そのうち、知人の葬儀があり、仕方なく礼服を着てスニーカーを履いて式に臨みます。それを知人が見咎めて訳を尋ねてきたので事情を話したところ、それはウオノメではないかと言われ、早速、皮膚科に掛かると間違いなくウオノメであったとのことです。 ◇ 思うに、現代社会は、医療に限らずあらゆる分野で些末的な見方が進み、全体的に捉える視点が見失われつつあるようです。 教育について見ても、子供のころから、知識を詰め込み、点数にこだわるような面のみが重視され、善悪の判断や、思いやり、助け合いなど、人間として育てるという面が軽視されています。 思春期から青春というもっとも輝かしい、一生に一度しかない貴重な時間を、小学生も、中学生も、高校生も「良い学校」を目指して、受験勉強一筋です。読書をし、のびのびと生活を楽しむ、というような時間を取り戻したいものです。その方が、結果的には有能な人間として育つのではないかと思います 企業においても、業績を上げることのみが優先され、そのためには社員を切り捨てても仕方がないという考えが根付いているようです。その延長上に人間を部品と見做して、どんどん使い捨てにするブラック企業なるものが増えています。 しかし、企業とは、本来、世のため人のために役立つことを目的として起こされるべきものです。競争に勝たなければという側面は当然あるにしても、現状は人を幸せにするという面があまりにもないがしろにされています。 ◇ 法華経の化城諭品第七に次のような経文があります。 願わくは此の功徳を以て普く一切に及ぼし我等と衆生と皆倶に仏道を成ぜん(枠中の語の訓読) 【口語訳】願いとするところは、自分たち(出家者)が得たこの功徳をすべての人々に振り向けて、みんなで一緒に仏の境地に達したいものです。 これは非常に有名な文句で、多くの宗派で読まれ、お勤めの最後に読まれるので〈結願の文〉とも、その内容から〈普回向の文〉とも言われます。 自分だけの救いでなく、すべての人が幸せになるようにとの大乗仏教の精神を伝えています。 ◇ 人々が助け合い、知恵を出し合ってよい社会を形成してゆくこと、共生の社会を示唆しているのがバビロニア型で、仏教の教える処でもあります。医療など、それぞれが専門化し高度化してゆくことは必要としても、バビロニア型という原点を大事にしたいものです。 |
| 歯医者さんの話によると、世の中には「入れ歯が合う人」と「合わない人」がいるそうです。
◇ 「現実をどう受け入れるか」、このことは、私たちの幸せ観に深く関わる問題です。 私たちは普段、もっとお金持ちの家に生まれていれば…、もっと頭がよかったら… と、自分の今の境遇を嘆きがちです。しかし、今回の大震災のような厳しい運命に遭遇したとき、「平凡に生きていることだけでいかに幸せだったか」を痛切に実感します。そして、何事もなく今日という日を迎えられるということは、実は奇跡的に素晴らしいことなのだと気づきます。 このように考えると、幸せになるには、「~ならばいいのに」(欲望型思考)と思わずに、「~でなくてよかった」(現状肯定型思考)と考えることだと思います。 ◇ それでは、不運な事態が起きてしまった時は、どうするか。 その時は、「人間万事 昔、中国北方の塞近くに住む占いの巧みな老人(塞翁)の馬が、胡(こ)という異民族の土地に逃げてしまう。人々が気の毒がると、老人は「これは福となるだろう」と言う。やがて、その馬は胡の駿馬(しゅんめ)を連れて戻ってきた。良くないことに出逢った時に、「人間万事塞翁が馬!これが福となるかもしれない。」と思うと、落ち込んだ気持ちも少しは和らぐでしょう。 ◇ このように、幸せ観はプラス思考から生まれます。 フランスの哲学者・アランは、「悲観主義は感情で、楽観主義は意志の力による」と言っています。私たちは楽観的なことは天性のものと思いがちですが、実はそれなりの意志の力(努力)が必要だということです。アランはまた、「幸福だから笑うのではない、笑うから幸福なのだ。」とも言っています。これも、幸福であるためには、「常に笑いがあるようにする」という努力が必要だということでしょう。 ◇ 以上の考え方は、正に法華経の説く「諸法実相」の教えです。(実台寺だより・第39・50号参照) 「この世のあらゆる存在は、真実の姿を示しており、それぞれそのままで価値があるのだ」ということで、だから、他と比較することなく、現実がそのままで充分に価値があるのだと受け止めなさい、ということす。 ところで、法華経の「自我偈」(如来寿量品第十六)の最後に、 毎自作是念 以何令衆生とあります。仏の大慈悲を表していることばです。 私たちは、このような教え(諸法実相など)を実践することによって、仏さまの救いに |
世阿弥は、室町時代に猿楽(現在の能)を大成した人ですが、天才と言われるだけあって、芸を学ぶに当たっての多くの有意義な言葉を残しています。
「初心忘るべからず」(『花鏡』)もその一つです。一般には、物事を習い始めのころの新鮮な意気込みを忘れずに持続しなさい、というような意味で用います。しかし、実際には世阿弥はもっと深い意味を込めているのです。 ◇ ここでの「初心」とは、習い始めのころの芸の力量のことです。「最初はこんなことしかできなかったのだ」と初心のころの力量を覚えていることによって、現在の自分の力がどのくらいの位置に達しているかが分かるというのです。 さらに、「時々の初心忘るべからず」とも言っています。これは、習い始めて1年後のあるいは5年後のその時々の力量がどの程度だったかを覚えていることによって、さらに自分の現在の力量をしっかり把握できるということです。 ◇ そういえば、私にも思い当たる体験があります。高校3年の時のことですが、たまたま高校1年のころの英語のノートが出てきました。それを見ると、ある一つの単語(forecast=予報)に真っ赤な線が何本も引いてあり、当時それを一所懸命に覚えようとしていたことが分かります。今ではそんなことは当たり前のこととして知っていた状態なので、「あー、これだけ自分に力が付いていたんだ。」と実感したのを覚えています。この場合、「高1の時の実力」が、「時々の初心」です。 このように「初心忘るべからず」は、芸を学ぶにしてもスポーツをするにしても、自分の現在の力量を知るのに大切な一句です。 世阿弥自身が、これを「当流に、万能一徳の一句あり」(『花鏡』)と記し、「あらゆる効能がこの一句に込められている」としているのも肯けます。 ◇ また、世阿弥は「離見の見」(『花鏡』)ということも言っています。 一般に、芸を演ずる役者は、その役になりきって初めて迫真の演技ができるといわれます。しかし、「熱演している自分の刹那々々にのめり込んでいる舞台というものは、得てして観客は逆に白々しい気分になるものである」(観世寿夫氏)とあるように、本当に感動を呼ぶには、自分の演技が観客からどう見られているかという視点も必要となります。 客席から舞台を見るのと同じように自分を見ることができる境地、これが「離見の見」です。 大リーグのイチローが「イチローという選手に対する見方は、僕が一番厳しかった。」と述べたことがありますが、まさしくこの境地を言っているのでしょう。 ◇ 自己を知ることの大切さとその方法についての世阿弥のことばを記しましたが、日蓮聖人は、『重須殿女房御返事』というお手紙で、 「地獄は遥か地の下にあり、仏さまは西方十万億土の彼方にいらっしゃると説く経文もあるけれどもよくよく考えてみると、地獄も仏も私たち五尺の身体の内に存在すると思われる」 と述べ、それに続けて 「私たち凡人は、近すぎる睫毛と、遠すぎる宇宙の果てを見ることはありません。だから、(身近かすぎて)自分たちの誰の心の中にも、仏さまはいらっしゃるのだということに気付いていないのですよ。」(枠中の語・私訳)と書いておられます。 私たちは、確かに「一切衆生 悉有仏性」の教え、自分も他の誰もが仏性を宿した尊い存在なのだということを、身近か過ぎるゆえに忘れがちです。 自己の中に仏性があるという自覚を常に持ちたいものです。 |
外国の例を見ても、挨拶には「 では、「こんにちは」には、どんな思いが込められているのでしょうか。 ◇ 私たちの住む日本列島は、太古の昔から繰り返し大きな地震に見舞われ、津波に襲われてきました。ここしばらくの間は、大地震のはざ間にあり平穏な時期が続きましたが、阪神大震災を転機として、また活発な活動期に入ったといわれます。いつどこででも大地震や火山の噴火が起こりうる状況になっています。また、毎年必ず台風が襲来し、洪水、土砂崩れも後を絶ちません。 このように見ると、日本列島はまさに災害列島であり、明日どうなるかは誰にも知れないという思い、「無常」の思いを人々の心に刻んできました。 ◇ 「こんにちは」は、このような無常の思いを背景として生まれた言葉といえましょう。 芥川賞作家で僧侶でもある 私たち日本人は、人為ではどうにもならない大自然の猛威に対し、このような祈りの心、ガマンという ◇ 法華経の法師功徳品第十九に 「若持法華経 其身甚清浄」とあります。 この経文では、「 法華経の教えは、「諸法実相」に集約されるといわれます。「諸法」とは、すべての事物、「実相」とは、ありのままの姿・真実のこと(「岩波仏教辞典」)ですから、「この世のあらゆる存在は、真実の姿を示しており、それぞれそのままで価値があるのだ」ということです。(実台寺だより・第39号参照)すなわち、成績が悪かろうが、走るのが遅かろうが、貧乏であろうが、病弱であろうが、他と比較することなく、そのままで充分に価値があるのだと考えるのです。このことが、本当に理解できれば、私たちはどんな状況でも、今置かれた立場を不満なく受け入れられることに繋がり、その身は清浄である、即ち、安らぎの悟りの境地に入れるであろうということになります。 ◇ 私たちは、地震・津波・火山の噴火・台風など、世界でも有数の災害列島で民族として上手に付き合ってきているといえましょう。 そこには、地球は揺れるもの、世界は変わりゆくものという日本人独自の世界観があります。そして、このような世界観が築かれた根底には、「諸法実相」をはじめとする数々の仏教の教え、諦め・忍辱などの考え方が 災害列島に生きるがゆえに、私たちは良い民族性を 日本の美点を自覚し大事にしていきたいものと思います。 |
従業員たちが他に連絡を取っている間に、暴漢たちは倒れたダマラさんに暴行を続け死亡させました。監視カメラの記録でも、彼はまったく反撃していませんでした。 ダマラさんは、普段から、「日本で争いごとになっても、絶対に手は出すな。一人一人がネパール大使になったつもりで振舞おう。」と言っていたとのことです。 最後まで耐えに耐え非暴力を貫いた結果の悲劇でした。 ◇ 「非暴力」とは、物事の解決のために暴力を用いないということです。 その元祖とみなされるガンジーは、インドをイギリスの植民地から独立に導きました。「非暴力・不服従」を提唱し、「非暴力の戦士はいかなる仕打ちも覚悟しなければならない。これを守れる者だけが、運動に参加できる」、と呼びかけ、これを受けて、ガンジーの弟子の一人は非暴力運動家の兵士を訓練・養成しました。 ある時、訓練を受けた非武装の兵士や群衆が市場に集まったところへ、イギリスの政府軍が発砲しました。群衆は非暴力の運動に教化されていたので、前列の人々が倒れると後列の人々が前進し銃火に晒されるという状況で、この衝突は朝11時から夕方5時まで続きました。(イギリスの連隊の一部は彼等に発砲することを拒絶したといわれます。) このような犠牲を重ねての独立の達成でしたが、戦闘を行っていたらもっと多くの犠牲者が出、独立もならなかったと思われます。非暴力の勝利といえましょう。 この戦術は、米国の黒人差別に対抗したキング牧師、ミャンマーの軍事独裁政権に対したアウンサンスーチー氏などに受け継がれています。 ◇ 法華経第二十に「常不軽菩薩品」があり、このようなことが書かれています。 一人の仏道修行者がいた。彼は人に出会うと誰に対しても合掌して礼拝し、「私はあなた方を敬います。決して軽んじたりしません。なぜなら、あなた方はみんな必ず仏になる方々だからです。」と言って讃嘆した。彼は、経典を読誦したりはせず、人を見ると近付いて行って、一つ覚えのように同じ言葉を繰り返すので、人々は気味悪がり、怒って、この修行者に罵声を浴びせ、杖で打ったり石や瓦を投げつけたりするが、彼は決して怒らず、遠くへ走って逃げては、声高に「あなた方を軽んじません。」と、繰り返すので「常(じょう)不軽(ふぎょう)(いつも軽んじない)」というあだ名がついた。この一途の行によって、ついに人々を教化し自らも仏となった。このように、常不軽菩薩は罵られ迫害されても、言い返したりせず、ひたすら合掌礼拝するだけでした。この姿勢は、仏教徒の非暴力の規範としてよく引用されるところです。 ◇ 非暴力は、はるかに暴力に勝ります。強い心がなければできません。そして、長い目で見れば世論の共感を呼び、必ず勝利するものと思われます。 ダマラさんの場合は、悪い結末になりましたが、この事件について「ネパール人の死 申し訳ない」という中学生の投書が載りました。(朝日新聞2/25) ダマラさんが普段から非暴力を説いており、それを自ら実践したことに感動したこと。相手を尊重し、静かに矛を収める、これが日本人の心ではないか、と筆を進め、「心から謝罪すると共に、決して手を出さなかった彼の姿から学ぶべきだ。」と結んでいます。 このような影響を多くの人の心に残せたことも「非暴力のちから」と言えましょう。 |
人との別れとは、その別れが悲しければ悲しいほど、ある意味では幸せなのだといわれます。
自分にとってどうでもいい人がいなくなっても、悲しみは感じないものです。悲しいと感じるのは、その人が自分にとってかけがえのない人だったから、つまり、何ものにもとって代われない密度の濃い時間を共有してきた間柄だったからといえましょう。 悲しみが大きいほど、共に過ごした時間は濃密だったはずであり、そのような幸せな時間をかつて過ごすことができたということ、そのような思い出がもてたということが、ある意味で幸せといえるのでしょう。 ◇ 未曽有といわれる大震災からちょうど一年。突然一瞬のうちに愛する肉親を失ってしまった人々の悲しみは、想像を絶して深く、未だに苦悩の中から立ち上がれないでいる多くの人々の姿がテレビ・新聞等で報じられています。 これらの方々が立ち直るには、時の経過が必要です。しかし、立ち直れた暁には、この幸せだった思い出が、その人を後押しする力となってくれることでしょう。 ◇  お釈迦様は、インドの北方クシナガラというところの沙羅双樹の下で、涅槃に入られました。 お釈迦様は、インドの北方クシナガラというところの沙羅双樹の下で、涅槃に入られました。その様子は、「涅槃図(右図)」としてたくさん描かれていますが、その安らかなお姿は人の最後の理想的な姿をお手本として示してくれているように思えます。 涅槃図には、そのお釈迦様を取り囲み、たくさんの弟子や村人や森の動物たちまでもが嘆き悲しんでいる様子が描かれています。 お釈迦様は、それらの嘆き悲しむ衆生をご覧になって、 「あなた方は何も嘆くことはありません。今、私の身体は滅していきますが、私の説いた教えはあなた方の心に残っているはずです。仏とは、私の身体ではなく私の説いた教えです。その教えを忘れずに、実践してゆくならば私、即ち仏は、常にこの世に在って法を説き、あなた方を導いていることになるでしょう。」と言われました。 法華経にも、「仏はいつもこの世に在って法を説き続けている。」(枠中の語)とあります。 確かに、お釈迦様の教えは、たくさんの経典となって残されており、今も仏はこの世に在って私たちを導いてくださっているといえましょう。 ◇ 亡くなった人を考えるときも、おなじように考えられるのではないでしょうか。 故人がかつて諭してくれた言葉や働いていた姿などを覚えていることによって、故人は絶えず私たちの心の中に生き続け私たちを見守ってくれていると考えるのです。 仏事において、私たちはよく、亡き人の「冥福を祈る」といいます。これは、故人があの世で安らかでありますようにと祈ることですが、故人に安らかであっていただくには、私たち残されたものが、故人の期待に応えられるよう、元気にしっかりとやって行くことだと思います。  そして、そのような思いをもって生きることが悲しみから少しでも早く立ち直るための一つの方法でもあるのです。 そして、そのような思いをもって生きることが悲しみから少しでも早く立ち直るための一つの方法でもあるのです。 |
今、世界中が苦悩しています。
思うに、私たち人類の文明は徐々に崩壊に向かっており、その漠然とした予感が閉塞感として時代を覆っているように思えます。 ◇ 私たちは、自分たちの生活の快適化のために、地球の資源を浪費し、環境を破壊してきました。 例えば、石油について考えます。 ジャンボ旅客機を羽田から北海道の千歳空港まで飛ばすのにドラム缶(二百㍑)五十本分の燃料を必要とします。世界では、一日に何千便もの飛行機が空を飛んでいるわけであり、その他、自動車、船舶、火力発電、工場、化学部品の原料としての使用などを考えると、その消費量の大きさが想像されます。統計によると、現在世界全体では、一日に八十六億五千万リットル(ドラム缶四千三百万本分)の石油を消費しているとのことです。 そして、石油は既に涸渇期に入り、あと数十年で無くなってしまうとのこと。地球が何十億年もの時間をかけて蓄えてきた資源を、現代人は自分たちの生活を快適にするために、わずか百年余りで使い切ってしまおうとしています。 ◇ そして、その結果、年間六十億トンもの二酸化炭素を大気中に放出して、温暖化、砂漠の拡大等々を生み出しています。また、原子力発電からは何億年も経たないと無くならない放射能のゴミをたくさん排出しています。これらの負の遺産はすべて次の世代の、私たちの子や孫たちが背負わねばならないのです。自分たちが散々楽しんでおいてそのつけを次世代に廻しているというのが今の構図です。 ◇ 法華経(比喩品)に、「火宅の譬え」という話があります。 ー大富豪の大邸宅に火事が起きる。中には、多くの子供たちがいるが、火の恐ろしさも知らず遊びに夢中で逃げようとはしない。それを富豪の父が、方便を以て救い出すーという話です。 現在の環境破壊の様相は、正に法華経の説く「火宅(燃えている家)」と言えましょう。火事は人類をも滅ぼすかもしれないのに、その恐ろしさに気が付かず、未だに放漫に浪費を続け、二酸化炭素抑制の京都議定書の採択にさえ加わらない大国が存在するのも事実です。 ◇ 私たち日本人の生活にも、一考を要することがあるようです。 ある外国人曰く、「日本人はなぜトイレの便座まで温めなければいけないのか?」、「有り余る体力があるのに、どうしてトランクやゴルフバッグを宅配便で送るのか。」 その他、多量の残飯の排出、贈答品の過剰包装など、バブル期以後の使い捨ての文化から抜けきれていない実態があります。 ◇ しかし、今回の大震災を契機に人々の価値観も大きく変わったと言われます。 人生いつどうなるか分からないという《無常》を実感し、「昇進や金のために無理するよりは家庭・家族を大事に、健康で」とか、「無駄を省き飾らない質素な生活を」、さらには「人との出会いを大切にし、他人の役に立ちたい」などの意見が目立ちます。 「丈夫ナ体ヲ持チ、欲ハナク、質素ニツツマシク、人ノ話ヲヨク聞キ、他人ノ手助ケヲスル。」…宮沢賢治「雨ニモマケズ」が究極のお手本と言えましょうか。 いずれにしても、「物の豊かさから心の豊かさへ」、「便利さは多少失くしても安全・安心を」が、大震災後の流れと言えましょう。 |
今回の東日本大震災は、マグニチュード九・〇の大地震、十数メートルの高さに及ぶ大津波、さらにはレベル7という最高の深刻度となった原発事故が重なって、まさしく未曾有の大惨事となってしまいました。 二万人を超す死者・行方不明者、四十万人に及ぶ避難民、その他、建造物や道路・港湾などのインフラ破壊など甚大な被害となる中、仮設住宅での孤独死、各産業の業績悪化・倒産、その結果としての解雇・過労死、放射能汚染による故郷喪失・一家離散など、多くの人が大変な苦しみを味わい、我が国全体としても、政治の混乱も重なって、将来の展望が見えない沈滞ムードが漂っています。 ◇ しかし、このような大変な状況に出遭ったからこそ、再認識されてきたものがあります。それは、阪神大震災の時にも言われましたが、《日本人のモラルの高さ》です。 アメリカでは、「被災者の忍耐強さと秩序立った様子に驚きと称賛の声が上がっている。『日本ではなぜ略奪が起きないのか』が相次いで議論のテーマとして取り上げられている。」と報じられています。 各国の取材陣も、被災者のお互いに少ない食べ物を分け合う姿や、商店でも、このようなときには必ず見られる便乗値上げが見られず、むしろ「こういう時だから元気をつけて」と、普段の半値でパンを売る店や、人々が我慢強く何時間も列をなす姿を紹介し、日本以外ではまず考えられないことと報じています。 ハイチ地震の際の略奪や暴動、アメリカ・フロリダ州のハリケーン被災者の窮状に付け込み、ホテルの宿泊料や発電機の値段がそれぞれ4倍・8倍にも跳ね上がったことなどを思い出しても、確かに誇りとするに値するものといえましょう。 もちろん、震災に便乗した犯罪や問題行動がまったくなかったわけではないようです。各所で、従業員のいない店舗や住宅、ガソリンスタンドや車などのガソリンを狙った窃盗事件が相次いだり、募金詐欺事件も発生しました。 また、生活物資の買いだめが全国に拡大したり、原発事故などによる風評被害が問題視されています。 ◇ 日蓮聖人は、 「地獄はどこにあり、仏様はどこにいらっしゃるかと問われたときに、地獄は地中の奥深い処にあり、仏様は西方十万億土の遠い世界にいらっしゃると説く経文もあるけれども、よくよく考えると地獄も仏も私たちの心の中に存在すると言えるのだ。」(枠中の言葉)この文を引くまでもなく、人の中には善(仏)の心と悪(地獄)の心とが同時に存在します。私たちは、この仏の心(仏性)のほうを育てていくことが大切になります。仏教ではあらゆる生きとし生けるものは仏性を備えておりそれぞれが尊い存在だと説きます。 日本人は豊かな自然の恵みの中に育ち、あらゆる生きとし生けるものを大切にする生き方を自然に身に付けてきたと思われます。そして、その後ろ姿を見てその子供が育つ。このようにして、民族の文化・モラルといったものは受け継がれていくのです。 ◇ 今回の電力不足を契機に考えてみると、私たち日本人は高度成長期を境に、不必要に贅沢な暮しをし、資源を浪費してきたように思います。冷暖房は使い過ぎ、コンビニやテレビが24時間やっているのもおかしい、このような点を改め、以前のようなもう少し質素な暮らしに戻すべきだと思い  ます。 ます。無用な贅沢と浪費を排し、自然の恵みを享受するような生き方に舵を切れば、世界の認めるモラルの高さと相俟って日本は世界各国が刮目するさらにすばらしい国になるでしょう。 |
そして、調べていくうちに、これは、単なるクマの問題ではなく、日本の森の危機であり、水資源の危機であり、私たちの生存にも関わる問題と気付きます。 ◇ クマは、なぜ人里に下りて来て殺されるのか。それは、奥山の荒廃が原因と分かります。 昔は、奥山はブナやミズナラなどの落葉広葉樹の巨木が生える原生の森でした。広い空間がいたる所にあって風通しが良く、地面はフカフカとして保水力抜群で、苔からは水が滴り落ちる、…このように、奥山とは、神々しさを感じるほど美しく、清らかさに満ちていたと言われます。 このような森は、植物だけでは成り立ちません。動物が歩きまわり、木に登って枝を折って空間を作り、木の実を食べて排泄するなど、動物は植物に寄生しているのではなく、密接な共生によって森をつくり上げているのです。 ◇ それが、戦後の開発や造林によって奥山はスギ・ヒノキの人工林に転換され、その後の国内林業の衰退によって人工林も放置されたまま荒れ放題となり、かつて豊かだった森の多くが死の森と化してしまいました。 その結果、山で食べ物を得られなくなった鳥獣が、里へ降りてくることになります。中でも、一番多量の食物を必要とするクマから人里への出没を余儀なくされることになったのです。 ◇ このようなことが分かり始め、この野生動物を守る機関が何もないと気付いた時に、これでは動物たちが可哀そうだと生徒たちは独自にその救済に立ち上がったのです。しかし、そのためにはあらゆる勉強が必要になってくる。多くの生徒たちが、信じられないような猛勉強を始めたと、指導に当たった先生は証言します。 そして、それが県知事を動かし、天皇・皇后両陛下への訴えを通して、植樹祭にはスギ・ヒノキに代わって広葉樹を植えることなり、狩猟禁止令の発令という成果まで上げるに至ったのです。 自分以外の弱者のためになさねばならないという崇高な目標を持った時、人は別人になったかのような信じられないような変わり方をするものだと、先生は述懐しています。 ◇ 「忘己利他」という言葉があります。「自分を忘れて他者のためにつくす。(他を幸せにすることで自分も幸せになる。)」という大乗仏教の根本精神を表わす言葉で、菩薩さまの生き方を表わす言葉でもあります。 思うに、自分一人が満足するのは、それだけのことであるが、相手が喜ぶのを見てこちらもうれしくなるというのは喜びが二倍になるともいえる訳で、それが忘己利他の真髄と言えましょう。 ◇ 人は誰でも仏になる種・仏性を宿していると言われます。人間の勝手な行ないが、野生動物を苦しめている、そのような現実が中学生たちの仏性を目覚めさせ、忘己利他の行動となって表れたのだと言えましょうか。  忘己利他は慈悲の究極なり (『山家学生式』) |
ここで問題なのは、その習慣的な考えの約八十パーセントがネガティブ(否定的)なものであって、つまり、ほとんどの人は、一日に四万五千回も後ろ向きの考えに囚われていることになるということです。 そして、そのような思考回路は、人が太古の昔から色々な危険から身を守るために身に付けた習性なのだそうです。(「脳にいいことだけをやりなさい!」三笠書房刊) ◇ このように、私たちの思考はネガティブなものに傾きがちです。そして、ネガティブな思考は、憂うつや不安を引き起こし、健康上もマイナスに作用し、ポジティブ(肯定的)な思考によって、脳内は穏やかになり、有益な影響がもたらされていることが実証されています。 それでは、ネガティブな思考を断ち切って、心の平安・幸せ感を得るにはどうしたらよいでしょうか。 ◇ 人間の表情について考えると、怒り・恐怖・驚きの表情は、民族・国籍に関わらず共通して良く似ているのだそうです。それは、それらが人間の生存に関わる表情で先天的に持ち合わせているものだからです。 ところが、喜びや笑顔の表情は、生存には直接かかわらないので、私たちは周囲の人の表情を見て後天的に学ばないとなかなか出てこないと言われます。確かに、いつでも笑顔で人に接するとか、大変な時でも笑顔を見せられるというのは誰にでもできることではありません。そして、努力によって、そのような表情を身につけることが、人間関係の潤滑油になり、幸せ感につながると言えましょう。 明るく前向きにと努力すれば、脳の仕組みも変わります。幸せな人は、努力によって幸せを獲得しているともいえるのです。 ◇ 仏教に三法印の教えがあります。 「印」は印章(しるし)・標識のことですから、三法印とは、「仏教を特徴づける三つの真理」のことです。 ①「諸行無常」(あらゆる一切のものはうつりかわる)の三つです。 「諸行無常・諸法無我の教えを実践し自己を練磨しつつ、涅槃寂静を目指す」ことで、わかりやすく言えば、「一切のものは移り変わる(諸行無常)のであるから、人の命も常住ではないと悟り、すべてのものは何らかの繋がりをもって存在する(諸法無我)のだから、我ひとりの思い通りにはならないものと理解して、欲を離れ安らぎの境地(涅槃寂静)に安住する」という解釈にもなりましょうか。 ◇ 私たちは、日常的にいろいろな悩みや不安に囚われます。そして、安らぎの境地を求めます。そこで努力し、一時的にその境地に達せられたとしても、また次なる不安に遭遇する、その繰り返しが、私たち凡夫の常です。 絶対的な安心の世界に至るには、やはり、宗教による心の安らぎが必要ということでしょう。 
心の安らぎは最上の幸福である (『法句経』) |
「悟りといふ事は如何なる場合にも、平気で死ぬる事かと思つて居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であつた。」(『病牀六尺』)とは、正岡子規のことばです。 子規は、若くして脊椎カリエスと言う難病に冒され、最後の数年間はほぼ寝たきりで、 「絶叫。号泣。益々絶叫する。益々号泣する。その苦その痛何とも形容することは出来ない。…誰かこの苦を助けて呉れるものはあるまいか。」(同)とあるように、連日治まることのない塗炭(とたん)の苦しみに耐えながら、死の二日前まで執筆活動を続けました。 冒頭の言は、そのような状況から到達した「悟り」についての理解であり、重みのあることばと言えましょう。 ◇ 宗教とは、心の平安を目指すもので、その境地を仏教では、「悟り」・「安心(あんじん)」などと名付けます。 お釈迦様は、菩提樹の下で悟りを開かれた時に、先ず「四諦(したい)」(四つの真理)を説かれました。 それは、先ず「人生は思い通りにはならないものであり、それを思い通りにしたいと思うところから苦が生じる」(苦諦 くたい)。従って、「苦の原因は私たちの欲望である」(集諦 じったい)。だから、「欲望を無くせば苦もなくなる」(滅諦 めったい)。そして、「欲望を無くす方法は八正道という徳目を実践することである」 (道諦 どうたい)と示されたのです。 ◇ 「悟り」を考えるとき、「人生は思い通りにはならないもの」という認識が重要な鍵になると考えます。 人は、生まれようという意志とは関係なく生まれ、老いたくなくても確実に老い、愛する人ともいつかは必ず別れなければならず、優れた能力を持ちたいと願ってもままならない。つまり、私たちの人生は思い通りにならないことだらけです。 そして、考えてみれば、私たち人間が、無限の宇宙の中にあって、大自然の運行に身を任せているだけのちっぽけな存在であることを思えば、むしろほとんどのことが思い通りにならなくて当たり前なのです。 このことが理解できれば、辛いこと苦しいことに出会っても、人生においてはそれがむしろ当たり前なのだと諦めることができるでしょう。 ◇ 諦める(=明きらめる)とは真理を悟ることです。それが間違いのない真理と分かれば、どんな不条理なことであっても受け入れざるを得ない、これが諦めるということです。 子規の場合も、自分の病は不治のものでいかにもがいても無駄であり、大変でも付き合っていくほかはないという心境に達したものと思われます。 ◇ 日蓮聖人は、『聖人御難事』という御書において (人生において)善いことがあったとしたらそれは思いもよらない有難いことなのであり、悪いことがあったとしてもそれが当たり前のことなのだと思いなさい。(枠中のことば・私訳)と示されています。 聖人が身延山に入山されてから、その指示のもとに弟子の日興上人は駿河の国で活発に布教活  動を行ない、多くの弟子や農民の信者を獲得していきました。しかし、それが権力から睨まれるところとなり、熱原(あつはら)という土地で信徒の農民二十名が捕えられ、三名が斬首、他は禁獄という苛酷な刑に処せられた出来事がありました。《熱原法難》と呼ばれます。 動を行ない、多くの弟子や農民の信者を獲得していきました。しかし、それが権力から睨まれるところとなり、熱原(あつはら)という土地で信徒の農民二十名が捕えられ、三名が斬首、他は禁獄という苛酷な刑に処せられた出来事がありました。《熱原法難》と呼ばれます。上は、この時に聖人が送られた励ましの手紙の一部です。 |
◇ 土浦事件の被告は、その後死刑を求刑されますが、それは自ら望んだものであり、これで自身の願望が成就したとして、一貫して反省や謝罪の態度は見せていません。そして、自ら控訴を取り下げて今年一月に死刑が確定しました。 ◇ その点、秋葉原事件の被告は、後日、被害者に謝罪の手紙を送り、「取り返しのつかないことをしてしまった」と反省し、「皆様から奪った命・人生・幸せの重さを感じながら刑を受けたい。」、「どうせ死刑だと開き直るのではなく、きちんとすべてを説明しようと思っている。」と書いています。 ◇ ところで、「懺悔」という言葉があります。 懺悔とは、「自分の犯した罪を仏や師の前で告白し、悔い改めること」です。つまり、懺悔は「告白する」と「悔い改める」の二つの行為から成り立っていることになります。 初めの「罪を告白する。」これによって心が解放され、すがすがしい気持ちになれる効果が得られます。 そして次に、「悔い改める。」これが大切なことと言えますが、これは、今までの煩悩に覆われた誤った生き方を改めて、誰もが本来持っている仏性を働かせる生き方をする。少しでも世のため人のために尽くそうという心を起こす、ということです。 ◇ この観点からみると、秋葉原事件の被告からは、自己の犯した罪を認め、悔い、告白し、少しでも償おうとの真摯な心が読み取れます。死罪は免れぬにしても、心の解放は得られているのではないでしょうか。 一方、土浦事件の被告は強がりの姿勢はありますが、心中には鉛のようなものが鬱屈したままの状態ではないかと思われます。 ◇ 日蓮聖人は、『光日房御書』で 小罪であっても悔い改めなければ悪道に堕ちることは避けられないが、大罪を犯しても悔い改めればその罪は消える。 (枠中の語・私訳)と述べておられます。 光日房という女性が、武士として戦い殺人を犯さざるを得なかった、亡き息子の成仏を気遣うのにたいして、母子が熱心に法華経を信心していたのであるから成仏は疑いないと教示している部分です。 ◇ 簡単にいえば、今までの生活の誤りを正し、もっと善い生活に入ろうという大決心をすること、これが懺悔です。懺悔を習慣とすることにより、自分の足りないところを少しずつ補い、徐々に自己の完成を目指すことが大切と言えましょう。 (注) 「懺悔」は、「サンゲ」と読み、元来、仏教用語です。他の宗教でもこれを使用し「ザンゲ」と通称し、それが一般の読み方になっています。 |
「友愛政治」―16年振りに選挙による政権交代を果たした鳩山内閣の掲げる政治理念です。
鳩山首相は10月26日の所信表明演説で、「政治には弱い立場の人々、少数の人々の視点が尊重されなければならない。これが友愛政治の原点だ。」と述べています。 ◇ 貧富の二極化が指摘されて久しくなりますが、近年特に貧困が拡大しており、低所得者層の実態は深刻だといわれます。 「いまや、非正規雇用は全雇用の3分の1に達している。フリーターの平均年収は140万円、働いても食べていけない人が増えている。国民の25%が貯蓄ゼロ、収入が途絶えた途端にスッカラカン。生活保護を受けるしかなくなるが、若い人は申請しても99%が追い返される。」とは、貧困ネットワーク事務局長を勤める湯浅誠氏の話です。 ◇ この話を裏付けるように、今年4月に北九州市で39歳の男性が餓死した事件がありました。彼の場合、高校時代はラグビーをやっていたくらい元気でしたが、会社の仕事が苛酷で身体を壊し退職、アルバイトを転々とした末の結末だったようです。 一昨年にも「おにぎりが食べたい」と言い残して餓死した52歳の男性がいました。この人は生活保護を申請しても却下され「生活困窮者は死ねということか」とノートに書き遺していたと言います。 ◇ 私たちの身近でも、長時間労働や低賃金に苦しんでいる例はたくさん耳にします。 実際、当山にも以前にも増して様々な悩みを抱えた人が相談にくるようになりました。お寺ではその人たちの話をじっくり聞いてあげることしかできませんが、本当に苦しい顔で来た人が、帰るときは心なしか少しゆったりした顔つきになって帰ります。 しかし、貧困の解決にはやはり政治の力が必要です。 「友愛政治」の実現を期待したいものです。 ◇ 「四弘誓願」(=「四誓」)と呼ばれる四句の偈(詩句)があります。 「誓願」とは、梵語で〈プラニダーナ〉といい「前に置く」の意ですので、修行を始める前に立てる誓いということになります。「弘」は広大なの意ですから、「四弘誓願」とは、どの仏さま・菩薩さまにも共通する四つの広大な誓願ということで「総願」と言われます。 従って、多少の字句の違いはありますが、仏教のすべての宗派で唱えられています。 ◇ 「衆生無辺誓願度」は、その第一句です。「無辺」は「際限なく多い」、「度」は「彼岸に渡す=救う」ですから、 苦悩にあえいでいる衆生は限りなくたくさんいるがそれをすべて救おうと誓願します、 という意味になります。 前述のように、世間では沢山の人が苦しんでいます。仏は、それらをすべて救いたいと誓い願うのです。これが大乗仏教の菩薩行の心です。 私たちも、少しでも仏陀の悟りに近づくと共に、世の中のすべての人が幸せであれかしとの思いを込めて「四誓」を唱え、努めたいものです。 四弘誓願(しぐせいがん)  衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど) 衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)煩悩無数誓願断(ぼんのうむしゅせいがんだん) 法門無尽誓願知(ほうもんむじんせいがんち) 仏道無上誓願成(ぶつどうむじょうせいがんじょう) 南無妙法蓮華経(三唱) |
「智者と思しき人は偏執かぎりなし」(『隋自意御書』)とは、日蓮聖人のことばです。
◇ 最近、「足利事件再審決定」のニュースが大きく報じられました。足利事件とは、今から十一年前に起きた幼女の誘拐殺人事件です。事件の一年半後に、幼稚園バス運転手のSさんが警察に突如連行され、その日のうちに自白して逮捕されました。 その後、Sさんは否認に転じ無実を訴えます。しかし、幼女の下着についていた体液のDNA鑑定の結果がSさんのものと一致したということがほぼ決め手となって、最高裁まで争いますが無期懲役刑が確定します。 ◇ では、Sさんはやってもいないことをなぜ自白してしまったのでしょうか。そこには取調官の刑事のプロとしての技術があるのです。今の取り調べは、かつてのように暴力は用いないようですが、間違いなく犯人だと目星をつけた人間には、密室の中で長時間に亘り何人もの刑事が取り囲み、人間の心の弱さをうまくついて自白に追い込む技術が進んでいるとのことです。 自白してしまった心境をSさんは「しゃべっちゃったんです、つい…。なにもやっていないのにすごく悔しかった。でも、裁判になれば裁判官は立派な人たちだから、必ず自分の無実を見抜いてくれると思った。」と言っています。 当時のDNA鑑定は今ほど精度が高くなく、しかもサンプル採取の仕方も厳密ではなかったようですが、最先端の鑑定法という錦の御旗に取調官の刑事は絶対間違いないと確信したのでしょう。それに「やってなければ自白するはずがない。」という思い込みが加わって、検事・裁判官や第一審の弁護士までもが信じてしまい、よく調べれば矛盾が見つかるはずの「自白の検証」を怠ったということになります。 ◇ 思い込み捜査といえば、第一通報者の河野義行さんが警察に犯人と決め付けられ、ほぼ一年近くに亘ってひどい人権侵害を受けた松本サリン事件がその典型でしょう。 その時のことを河野さんは「家族四人がサリンを吸って救急車で運ばれ、自分も苦しんでいる中で事情聴取をされ、辛くて肘を付いていると『姿勢を正せ』と怒鳴られ『本当のことを言ってください』とはじめから犯罪者扱いされた」と言っています。 ◇ このように、人は一旦間違いないと思い込むとなかなかその思いから離れらないものです。特にベテラン刑事や検事・裁判官・弁護士など、「智者と思しき人」ほどその傾向が強いと思われるのは、正に冒頭の言葉のとおりです。 ◇ 仏道においては、中道にして柔軟な心が大切と言われます。 従って、「仏の悟りに至るには、思い上がり(我慢)や偏った見方(偏執)にとらわれる心をなくしてただ南無妙法蓮華経とお唱えするのが良いのである」(枠中の言葉)となるのです。 |
|
すべてに価値あり 平成21年3月1日
|