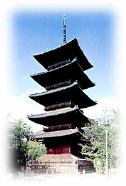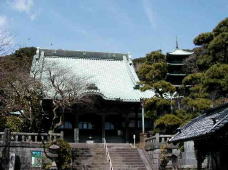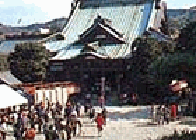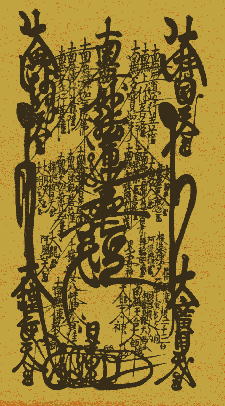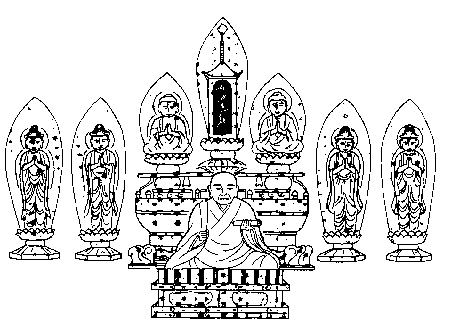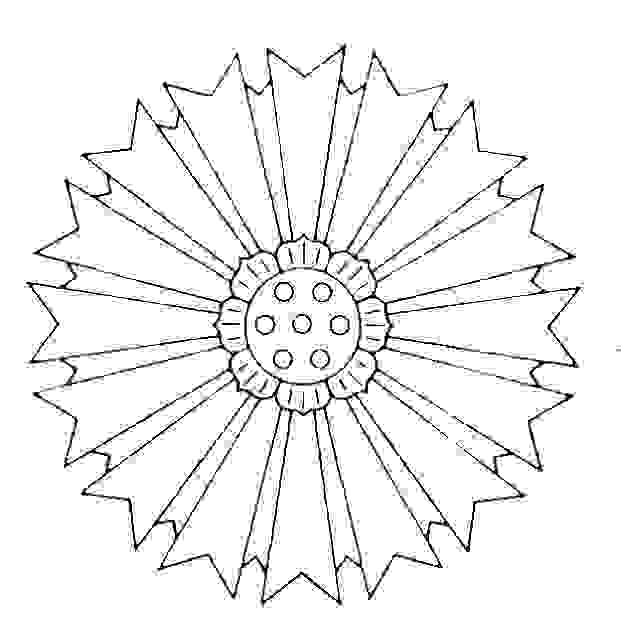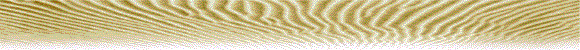
���@�@�Ɋւ��鎖
| ���@�@�Ɋւ���m�� | ���@���l�̂����U�Ɨ�Տ��� | ||
| 1 | �u�䌅�ɋk�v��Ə@�͖� | 1 | ���@�@�̎��@ |
| 2 | ���@�@�̖{�� | 2 | �����R�a���� |
| 3 | �u�c��ہv�Ɓu�؏ށv | 3 | ����R������ |
| 4 | ��{�R������ | ||
| 5 | �C���R������ | ||
| 6 | �������R���E�� | ||
| 7 | ����R������ | ||
| 8 | �ˌ��R���{�� | ||
| 9 | ���@�؎R���Ǝ� | ||
| 10 | �g���R�v���� | ||
| 11 | ���h�R�{�厛 | ||
| 12 | �����R�@�،o�� | ||
| 13 | �x�m�R�{�厛 | ||
| 14 | ��R������ | ||
| 15 | ����R�{���� | ||
|
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂� �@�@�@�@�@�@�@
�`���֖߂�
�`���֖߂�
�`���֖߂� �@�@
�`���֖߂�
�`���֖߂� �@
�`���֖߂�
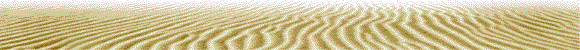 |