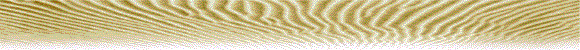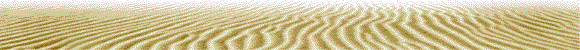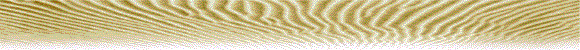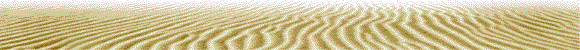| 瑁@��@ |
�{�@�� |
| ���i���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
�]�n�O�o�i��\�� |
| ���֕i���@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
�@����ʕi��\�Z�@�@�@�@�@�@�@ �� �@ |
| 栚g�i��O |
���ʌ����i��\�� |
| �M��i��l |
��������i��\�� |
| �@�i��� |
�@�t�����i��\�� |
| ���L�i��Z |
��s�y��F�i���\ |
| ����g�i�掵 |
�@���_�͕i���\��@�@�@�@�@ �� |
| �ܕS��q���L�i�攪 |
���ݕi���\��@�@�@�@�@�@�@�@ �� |
| ���{���{�l�L�i��� |
��F�{���i���\�O |
| �@�t�i��\ |
������F�i���\�l |
| �������i��\�� |
�ϐ�����F����i���\�� �@�� |
| ��k�B���i��\��@�@�@�@�� |
�ɗ���i���\�Z�@�@�@�@�@�@�@ ���@�@ |
| �����i��\�O |
���������{���i���\���@�@�@ �� |
| ���y�s�i��\�l |
������F��ᢕi���\���@�@�@ �� |