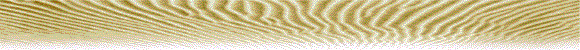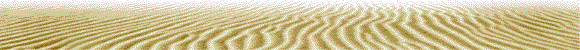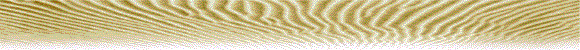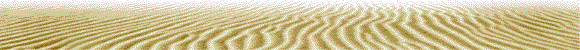〈日蓮聖人の御遺文〉講読
「開目抄」
(文永9年2月 佐渡塚原三昧堂 51歳 真蹟於身延焼失)
文永8年(1271)11月、佐渡に到着と同時に執筆、翌年2月に完成。
○執筆の理由
①日蓮聖人の布教と迫害に対する弟子・信者の疑いを払うため。
②末法の導師が日蓮聖人であることを明らかにするため。
③佐渡で死を覚悟した日蓮聖人が「かたみ」として弟子達に残すため。
○題名の意味
「目を開く」こと。即ち、「世間の人の迷いを除いて、世間の人に法華経に対して、また、法華経の行者に対しての正しい理解を与える。」という意味。
【本文抄出・口語訳】
儒家の孝養は今生にかぎる。未来の父母を扶けざれば、外家の聖賢は有名無実なり。
儒教の教えでも孝ということは重んじるが、それは現世だけに限られる。来世において親を救うことを説いていないので、仏教以外で聖人とか・賢人とかいっても、実際は名のみで本当の聖人・賢人とは言われない。
○儒家…儒者の家。 また、儒者。
○孝養…親に孝行をつくすこと。「きょうよう」とも。
○外家…仏道以外の教えを信じる者。ここでは、儒家のこと。
外道は過未をしれども父母を扶くる道なし。仏道こそ父母の後世を扶くれば聖賢の名はあるべけれ。
また、バラモン教などでは過去世・未来世のことは説いているけれども、(一切の人間が仏になることを説かないので)親の後生を助ける道がない。仏教こそ来世のことも、一切衆生の成仏のことも説いて、親の後生を助け成仏を叶えるので、仏教を学ぶ者こそ聖人・賢人という名で呼ばれるべきなのである。
○外道…仏教以外の教え。また、その教えを奉ずる者。ここでは、インドの宗教(バラモンなど)。
しかれども法華経已前等の大小乗の経宗は、自身の得道猶かなひがたし。何に況や父母をや。
けれども、(同じ仏教でも)法華経以前の大乗・小乗の経典を拠り所にする宗派では、自分自身が成仏することが難しい。ましてや、親を助けて親の成仏を実現することができるはずがない。
○法華経已前の大小乗の経宗…。
○得道…仏道を修めてさとりをひらくこと。悟道を得ること。
但文のみありて義なし。今法華経の時こそ女人成仏の時、悲母の成仏も顕はれ、達多の悪人成仏の時、慈父の成仏も顕はるれ。此の経は内典の孝経なり。
ただ経文に後生の成仏が説かれるだけで、その実が伴っていない。今この法華経が説かれる時にこそ、女人成仏ということも示され、母の成仏ということも明らかになる。また、ダイバダッタのような悪人さえ成仏することが示され、父の成仏ということも明らかになる。
○女人成仏…古来より地位が低くみられてきた女性も仏になれると説いた教えで、法華経の教説の特色の一。女性には仏になれない五種のさしさわり(五障)があるとされるが、法華経提婆達多品では女性の成仏の現証として八歳の竜女の即身成仏が説かれる。日蓮も女人成仏を法華経の諸経に勝れている点として強調しており、女性信徒が多かったことも日蓮が女人成仏を強く主張した点をよく示している。(「日蓮宗小事典」より)
○悪人成仏…どのような重い罪を犯した者でも成仏をとげることができるということ。法華経の提婆達多品で、極悪の提婆達多に未来に仏となるへき保証(記別)が与えられたことによる。ここに法華経の救済の世界がすべての人々におよぶことがよく示されている。(同上)
【提婆達多】釈尊の従弟にあたり、八万法蔵を暗誦するほどの頭脳明晰な人物でありながら、世俗的名利への強い執着心によって釈尊に敵対し、「五逆罪」のなかの「殺阿羅漢・出仏身血・破和合僧」を犯して無間地獄に堕ちたと伝える。日蓮は、この提婆達多が法華経において成仏の保証を受けたことに着目し、謗法者であっても救われると提唱した。(「日蓮宗小事典」より)
【竜女成仏】法華経提婆達多品に説かれる八歳の竜女の成仏をいう。古来、女人は梵天・帝釈・魔王・転輪王・仏身となることができない(五障)とされてきたが、法華経では-転して、竜女が菩提心(悟りを求める心)を起こしてすみやかに成仏したことを明かす。日蓮は、この竜女成仏を女性の成仏の手本を示したものとして重視した。
(「日蓮宗小事典」より)
|