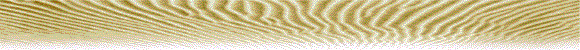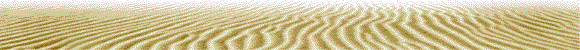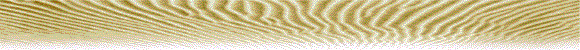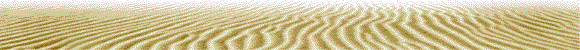(参考)「仏所行讚(ブッダチャリタ)」 :作者は、馬鳴(めみょう)菩薩。古代の仏伝
- 馬鳴(めみょう):アシヴァゴーシャ
- 二世紀ごろのインドの仏教詩人。バラモンの論師から仏教に帰依した。叙事詩「ブッダチャリタ(仏所行讚)」などの作品がある。
- 馬鳴(めみょう)という名の由来。(鳩摩羅什訳「馬鳴菩薩伝」)
- 馬鳴は本名を「弁才」といった。あるとき、王様が弁才の実力を臣下に示そうとして、七疋の馬を集めさせ、この馬に飼料を与えず腹をへらさせた。そして六日目の朝、十分に腹のへった馬たちのいる前に内外の人々を集めて、弁才を請じて法を説かせた。素晴らしい教えだったので、これを聞いた人で開悟しないものは一人もいなかった。
そこで頃はよしと、王は腹をへらした馬に対し、馬が一番に好きな草を与えさせた。ところが馬たちは涙を流して弁才の説く法を聞いていて、草には見向きもしなかった。このさまをみて人々は大いに驚き、馬も教えを聞いていたというので、この弁才のことを誰いうとなく、馬鳴と呼ぶようになり、馬鳴菩薩と崇めるようになった。
一.誕生から青年時代
1.誕生
- ○呼称
- 姓はゴータマ、名はシッダールタ(姓は「最上の牛」、名には「完成した」という意味がある。)漢訳では瞿曇 悉達多(くどんしっだった)。
- 「釈迦」は釈迦牟尼(しゃかむに)の略である。(梵:シャーキャ・ムニ、「釈迦族の聖者」の意) (釈迦は、部族名または国名で、牟尼は「聖者・修行者」の意味)
- 称号を加え、釈迦牟尼世尊、釈迦牟尼仏、釈迦牟尼如来とも、略して釈迦尊、釈尊、釈迦仏、釈迦如来ともいう。称号だけを残し、世尊、仏陀、ブッダ、如来とも略す。「仏陀・ブッダ」は、悟った者の意。
- 巷間では、お釈迦様、仏様と呼ばれることが多い。
- 仏典ではこの他にも多くの異名を持つ。うち代表的な10個を総称して「十号」と呼ぶ。
- ○誕生年・没年
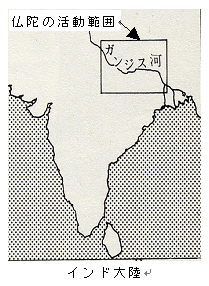
- ①南方仏教の説:紀元前624年~前544年
- ②大乗仏教の説:紀元前566年~486年
- ③中村元氏等の説:紀元前463年~383年
- 概略、今から約2500年前に生まれたといえる。
- ○家族
- 釈迦族:ヒマラヤ山脈の南側の麓、ネパールの西側、インドとの国境付近に住した。
- 父:シュッドーダナ(浄飯王:じょうぼんのう)。北インドにあるカピラバストゥ国の釈迦族の国王。
- 母:マーヤー(摩耶夫人:まやぶにん)。浄飯王の妃
- 誕生については伝説として次のように伝えられている。
母マーヤーは、子供を身ごもった後、白い象が天から降りてきておなかに入る夢を見た。また、占い師によって、おなかの中の子が将来悟りを開き偉い人になることを予言されたりもした。
出産間近になったマーヤーは里国へ帰郷の途中ルンビニーの花園に立ち寄つた。そこで休憩のため右手を無憂樹にかけようとしたとき、右脇から出産した。生まれ出た子供は東南西北に7歩あるき、右手で天、左手で地をさし「天上天下唯我独尊」と唱える。すると風が吹き花が舞い、天からは甘露の雨が降り注ぎ誕生を祝った。
中国や日本ではこの日を4月8日とさだめ、降誕会、誕生会としてお釈迦様の誕生を祝っている。
- ○母の死と義母
- マーヤーはお釈迦様の生後7日目に没するが、マーヤーの妹のマハープラジャーパティ摩訶波闍波提(まかはじゃはだい)が後妻に入り、王子として大切に育てられる。
- 「摩耶夫人その生むところの子の、端正にして天童のごとく、衆の美を悉く備え足りるを見て、過ぎし喜びに自ら勝てず、命終わって天上に生まれぬ。」(「仏所行讃」)
2.宮殿での生活
- 阿私陀仙人の予言:
- 「王子、若し王位に上り給わば、威武日に揚がり転輪王となって五天竺を統一し給わん。然し、若し出家し給わんには悲智円満の覚者となりたまいて普く人天を度し給わん。」
- 浄飯王は、王子を城に繋ぎとめておくために苦心する。
-
- ○豪奢な宮殿(「三時殿」)
- 父王は出家の気持ちが起こらないように、太子のために暑時殿・雨時殿・寒時殿という季節に応じた三つの宮殿を建てた。
- 三時殿:三時とは三つの季節(熱際時、雨際時、寒際時)で、「季節に応じて過ごす別荘」の意。
- ○無常の現実1(弱肉強食)
- ある年の春、農耕祭の時の出来事。小鳥が虫をついばんだと思うと、その小鳥を鷲が襲う出来事が起こった。この光景を見たお釈迦様は弱肉強食の現実を実感されたと伝えられている。
- ○妻を娶らす(結婚・子供・家庭)
- 17歳頃、耶輪陀羅:やしゅだら(ヤショーダラー)と結婚し、数年後、長男、羅 羅:らごら(ラーフラ)が生まれる。
ヤショーダラーとは、「すべてのものを兼ね備えた美女」の意。
ラーフラとは「障り。妨げとなるもの」という意味。
命名の由来には次のように伝えられている。修行の準備をしていたお釈迦様のところに長男誕生の使いがやってきて伝えたところ思わず「修行のさまたげとなるものが生まれた。」とつぶやいた。それを名前と勘違いした使いが城に戻って名前を「ラーフラ」と伝えたといわれている。
- ○無常の現実2(四門出遊)
- 城には東西南北に4つの門があった。御者のチャンナ・白馬のカンタカを伴って、各門から出て城外を見聞した。
- 東門から出た時:道ばたにいる老人に出会い、老いの姿に心を暗くされた。
- 南門から出た時:病人を見かけ、病に苦しむ姿に憂いの気持ちを抱いた。
- 西門から出た時:大勢が泣きながら野辺の送りに向かう葬列を目撃し、死の現実に直面した。
- 北門から出た時:気高く爽やかな姿の修行僧を見かけ、その姿に驚かれ、出家の決意を固められた。
-
- *後に釈尊はこのときのことを弟子たちに述懐した
「比丘らよ、私はとても恵まれ、とても大事にされたが、その私に次のような思いが生じた。『無知な凡夫は、自分自身老いるものでありながら、自分のことはさておき、他人が老いぼれたのを見て嫌悪する。私も同じく老いるものであって、老いを逃れられないその私が、他人が老いたのを見て嫌悪するということは、私にふさわしいことではない。』とこのように思い及んだとき、比丘らよ、私は若さの真っ只中で若さを誇る気持ちは全く消えうせてしまったのである。」
- ※生死の問題(老病死)を直視したとき、その人生苦の解決に向かう以外に道はないと釈尊は考えた。(われわれはただ問題を先送りしているだけにすぎない)
|